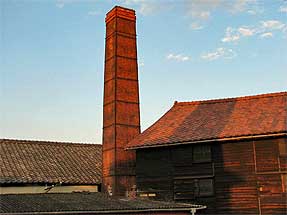|
|
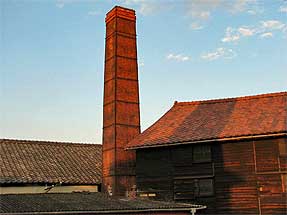 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
پ@ڈيٹٹپi‚ئ‚±‚ب‚كپj‚جڈؤ‚«•¨‚حپA‚PپC‚P‚O‚O”Nچ ‚©‚ç‚X‚O‚O”N‚ج—ًژj‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éپB“ْ–{کZŒأ—qپiڈيٹٹپAگ£ŒثپA‰z‘OپAگMٹyپA’O”gپA”ُ‘Oپj‚ج‚¤‚؟ˆê”شŒأ‚ˆê”ش‘ه‚«‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھڈيٹٹ‚إ‚ ‚éپB
پ@ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN‚بŒأڈيٹٹ‚جڈؤ‚«•¨‚حگ¢ٹE‚ة‚à‚»‚ج—ل‚ج‚ب‚¢‘fگ°‚炵‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB•½ˆہپAٹ™‘qپAژ؛’¬پAچ]Œث‚جٹeژ‘م‚جڑâ‚©‚ك‚جژه—v‚ب—qڈê‚ئ‚µ‚ؤ”ة‰h‚µپAچ]Œثژ‘م‚©‚ç“©Œ|‰ئ‚à‘½‚Œ»‚ê‚ؤپA‘½چت‚ب—qڈê‚ةگ¬’·‚µ‚½پB
پ@چ]Œث––ٹْ‚ةژn‚ك‚ç‚ꂽژé“Dڈؤ‚حپA–L‚©‚بƒچپ[ƒJƒ‹ƒJƒ‰پ[‚ً•Y‚ي‚¹‚ؤ‘½‚‚جگlپX‚©‚çگe‚µ‚ـ‚êپA‘Sچ‘‚ةژé“D‹}گ{‚ھ”„‚èڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‘ه‚«‚ب—q‚âگف”ُ‚ھ—L—ح‚ب•گٹي‚ئ‚ب‚ء‚ؤپAƒ^ƒCƒ‹پA‰qگ¶“©ٹيپA“©ٹاپAگA–ط”«“™‚ج‘هŒ^‚جڈؤ‚«•¨‚جژY’n‚ئ‚µ‚ؤپA–”“y‚à‚ج“©ٹي‚ج“ءژY’nڈيٹٹ‚ح‘Sچ‘‚إ‚à—Lگ”‚ب—qڈê‚إ‚ ‚éپB |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
پƒ“o—qپi“©‰h—qپjپ„پ@
پ@ڈيٹٹ‚ج“o—q‚حچ]Œثژ‘مپA“V•غ‚T”Nپi‚P‚W‚R‚Sپj‚ةŒïچ]•ûژُ‚ج•ƒپA•û‹~‚ھگ^ڈؤ‚¯•¨‚ًŒّ—¦‚و‚گ¶ژY‚·‚éˆ×‚ة“±“ü‚µ‚½‚ج‚ھژn‚ـ‚è‚ئ‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@چ]Œثٹْ‚جژه—¬‚إ‚ ‚ء‚½“S–C—qپi‘ه—qپj‚إ‚حپAگ^ڈؤ‚¯•¨‚ًŒّ—¦‚و‚گ¶ژY‚·‚邱‚ئ‚ھ“‚¢‚½‚ك“o—q‚ج“±“ü‚ح‰وٹْ“I‚بڈo—ˆژ–‚¾‚ء‚½پB
پ@‚±‚ج“©‰h—q‚ح–¾ژ،‚Q‚O”Nپi‚P‚W‚W‚Vپj‚ةŒڑ’zٹè‚¢‚ھˆ¤’mŒ§’mژ–‚ةڈo‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚جچ ‚ة’z‚©‚ꂽ—q‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پB“–ڈ‰‚ج—q‚حپAگd‚âڈ¼—t‚إ—q‚ً•°‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ھپA–¾ژ،‚R‚O”N‘م‚جŒم”¼‚ة‚ب‚é‚ئ‘وˆêژ؛–ع‚جڈؤگ¬‚ةگخ’Y‚ھژg‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAگـ’ڈژ®‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é“o—q‚ھڈيٹٹ‚إ‚حˆê”ت“I‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½پB
پ@“©‰h—q‚àپA‚»‚جچ ‚ةگـ’ڈژ®“o—q‚ة‚ب‚ء‚½‚ئگ„’肳‚ê‚éپBڈ]‚ء‚ؤŒ»چفژc‚ء‚ؤ‚¢‚é—q‚حپA–¾ژ،––ٹْ‚جژp‚ً‚ئ‚ا‚ك‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB
پ@–ٌ‚Q‚O“x‚جŒXژخ’n‚ة”ھ‚آ‚جڈؤگ¬ژ؛‚ًکA‚ث‚½“©‰h—q‚حپA‘S’·‚Q‚Q‚چپAچإ‘ه•‚XپD‚U‚چپAچإ‘ه“Vˆنچ‚‚RپD‚P‚چ‚ئ‘هŒ^‚ج“o—q‚ج•”—ق‚ة‘®‚·‚é‚ھ–¾ژ،––ٹْ‚جڈيٹٹ‚إ‚حپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب“o—q‚ھ‚U‚Oٹî‚ظ‚ا‚ ‚ء‚½‚ئ‹Lک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@‚»‚جŒمپAڈيٹٹ‚إ‚حگخ’Y—q‚ھˆê”ت“I‚ئ‚ب‚è“o—q‚جگ”‚ح‹}‘¬‚ةŒ¸‚茻چف‚إ‚ح‚±‚ج“©‰h—q‚ھژc‚邾‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج—q‚àڈ؛کa‚S‚X”Nپi‚P‚X‚V‚Sپj‚PŒژ‚ج—qڈo‚µ‚ًچإŒم‚ة‘€‹ئ‚ً’âژ~‚µپAڈ؛کa‚T‚V”Nپi‚P‚X‚W‚Qپj‚ةڈd—v—LŒ`–¯‘•¶‰»چà‚ئ‚µ‚ؤژw’肳‚ê•غ‘¶‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB
پƒ•°‚«Œûپ„
پ@“–ڈ‰‚ج“o—q‚حگdچق‚âڈ¼—t‚ً”R—؟‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA–¾ژ،Œم”¼‚ة‚حژù—v‚à‘‚¦پAگdچق‚âڈ¼—t‚ھ•s‘«‹C–،‚ة‚ب‚èپA‚±‚ê‚ة‘م‚ي‚é”R—؟‚ئ‚µ‚ؤگخ’Y‚ھ—p‚¢‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپAگخ’Y—q‚ً’z‘¢‚·‚é‚ة‚ح‘½ٹz‚جژ‘–{‚ً—v‚·‚邽‚كپAچف—ˆ‚ج“o—q‚ً—ک—p‚µپAگخ’Y‚ًژg‚¢”R—؟”ï‚جگك–ٌ‚ًŒv‚낤‚ئ‚µ‚½پB‚±‚ج‰ü—ا‚ح‘وˆêژ؛‚ج•°‚«ŒûپiƒzƒNƒ{پj‚ًڈ]—ˆ‚جˆê‚آ‚©‚çگ”Œآ‚ج•°‚«Œû‚ة•ھ‚¯پA‚»‚ꂼ‚ê‚ةƒچƒXƒgƒ‹‚ً‚آ‚¯گخ’Y‚ج”R—؟‚ً—eˆص‚ة‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‚±‚ê‚ة‚و‚è‘وˆêژ؛‚جڈؤگ¬‚ًگخ’YپA‘و“ٌژ؛ˆبچ~‚جڈؤگ¬‚ًگdچق‚âڈ¼—t‚ة‚و‚ء‚ؤڈؤگ¬‚·‚éپA‚¢‚ي‚ن‚éگـ’ڈژ؛‚ة‰ü—ا‚³‚ꂽپB‘وˆêژ؛‚إ‚ح–ٌ‚S’‹–é‘Sژ؛‚ً•°‚«ڈI‚ي‚é‚ج‚ة‚P‚P“ْˆت‚©‚©‚ء‚½پB
پƒڈo“üŒûپ„
پ@‚±‚±‚©‚çگ»•i‚ًƒGƒSƒچ“™‚ة“ü‚ê‚ؤ—q‹l‚ً‚·‚éپB‚»‚µ‚ؤ—q‹l‚ھڈI‚ي‚é‚ئƒ_ƒ“ƒ}پi’z—q‚ة—p‚¢‚郌ƒ“ƒK‚جˆêژيپj‚إڈo“üŒû‚ً‚س‚³‚®‚ھپA‚±‚جژڈo“üŒû‚جˆê•”‚ة•°‚«Œû‚ًگف‚¯‚ؤ‚¨‚پB
پ@‘وˆêژ؛‚ة‰—‚¢‚ؤگخ’Y‚ً•°‚‚ھپA‘و“ٌژ؛ˆبچ~‚ح‚±‚ج—¼‘¤‚ةگف‚¯‚ç‚ꂽ•°‚«Œû‚©‚ç‚PپD‚W‚چˆت‚جƒRƒڈپiٹغ‘¾‚©‚çٹpچق‚ً‚ئ‚éژ‚ة‚إ‚é’[گطپj‚ًژ؛‚جƒ~ƒ]•”‚ض“ٹ‚°“ü‚ê‚ؤ”Rڈؤ‚³‚¹‚éپBڈ¼—t‚جڈêچ‡‚حڈ¬‘©‚ة‚µ‚ؤƒTƒXƒ}ƒ^‚ً—p‚¢’†‰›•”‚ض“ٹ‚°“ü‚ê‚ؤ”Rڈؤ‚µ‚½پB‘وˆêژ؛‚إ•°‚©‚ꂽ‰‹‚حپAˆê“x“Vˆن‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤپA‚آ‚¢‚إڈلژq‚ة‚»‚ء‚ؤڈ°‚ـ‚إ‰؛‚ھ‚èپAŒٹ‚ً’ت‚¶‚ؤ‘و“ٌژ؛‚جپuƒAƒ[پvپiڈ°–تچ¶‰؛Œٹپj‚ضگپ‚«ڈم‚ھ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBژ؛‚ج“Vˆن‚â•ا–ت‚حپA’·‚¢ٹش‚جژg—p‚ة‚و‚èپAژ©‘Rçض‚ھ‚©‚©‚èپA‚ ‚½‚©‚àڈك“û“´‚ج”@‚Œ©‚¦‚éپB |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| پ@گخگ…—qپEˆî—tˆہگM‚³‚ٌ‚جچى“©‚ج—lژqپB–{گl‚ج—¹ڈ³‚ً“¾‚ؤژB‚éپB |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
پ@چâ–ىچW•½“Wپ[—پ[
پ@•½گ¬‚P‚X”Nپi‚Q‚O‚O‚Vپj’·ژOڈـŒ»‘م“©Œ|“Wپ@‘O‰q•”–هپ@’·ژOڈـژَڈـچى‰ئ
پ@—‚ئ‚ح‰F’ˆ‚جگ^—‚©پBپ@ |