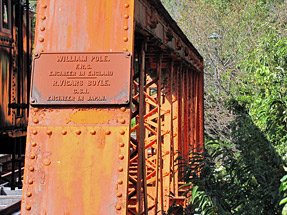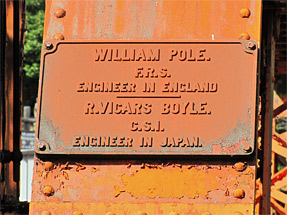|
|
 |
|
 |
|
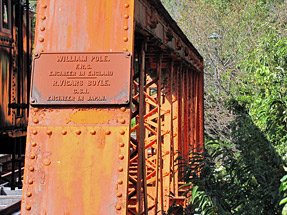 |
|
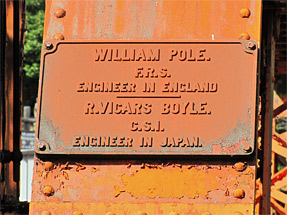 |
|
 |
|
六郷川鉄橋は日本初の複線用鉄橋である。明治5年(1872)に日本で初めて鉄道が開業した当時、新橋〜横浜間に架かる橋は全て木橋であった。開業直後、複線化の計画とともに桁橋への架け替えが進められた。
六郷川に架けられていた当時、橋は錬鉄製トラス6連からなる本橋と避溢橋(ひいつ橋:川が増水氾濫した場合を想定し河原に続く陸地部分に架ける橋)からなり、全長が約500mであった。明治村へ移築されたのは本橋部のトラス1連である。
設計は、お雇い外国人であるイギリス人土木技師ボイルnよるものであり、イギリス・リバプールのハミルトンズ・ウィンザー・アイアンワークス社で製作されたトラス桁を輸入した。登録有形文化財
旧所在地:東京都蒲田・神奈川県川崎間の六郷川
| 建設年 |
明治10年(1977) |
解体年 |
昭和40年(1965) |
| 移築年 |
昭和63年(1988) |
全長 |
約30m/幅約7.5m 桁高約3m |
| 構造 |
錬鉄製トラス桁 |
|
(博物館明治村(愛知県小牧市)にて撮影) |
|
 |
|
 |
|
この鉄橋には、両端には日本で鉄道が開業した当初に使われたのと同じ「双頭レール」、中央部には現在最も広く使われている「平底レール」という2種類のレールが敷かれている。
<双頭レール>
1837年、イギリスのロック(Locke.J)が考案したレール。イギリスで広く用いられ、わが国でも鉄道開通当時は、イギリス製の双頭レールが導入された。頭部が摩耗した場合に、上下にひっくり返して使用できることを特色としていた。現在、各国で用いられている平底レールはわが国では、明治9年(1876)に採用された。 |
|